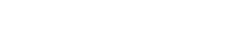
随想
◎悪夢の居場所◎
自分は“悪夢”をよく見る。乗った飛行機が、何度落ちたことか。小型フェリーが、嵐の波に飲まれて沈没したのは、何ヶ月前のことだったか。学会や講演会の発表当日になってもパワーポイントデータが完成しておらず、結局、間に合わなかった夢は、最近多くなってきた。大事な試験、おそらく医師国家試験か、医学部の卒業試験か、つまり、何年も積み上げてきて、ようやく“終了“となるころに、これまでの怠惰が祟って失敗する危機に直面するような、全身から血の気が失せる悪夢は、秋から冬に多い。特に、8月の“ひと夏の経験”が終わり、9月に入ると覿面である。センチメンタルな9月の雨(September Rain)ではなく、9月のトルネードである。瞬間的に真空になって、目の前が真っ暗になる奴だ。
スキーや登山など、装備が面倒な事は、無精者の自分はやらないが、なぜか雪崩に巻き込まれたこともある。パイプで組み立てた大きなコンサート会場のような建物が、大勢の人とともに崩れた現場にも居たし、ゾンビやオーメンに追っかけられたこともある。本当に疲れる奴だ。そうかと思えば、古いビルの中に迷い込んで、しかも、誰かに追われていて、なかなか地上にでることができない夢は、昔のアメリカTVの“逃亡者”の主人公・リチャード・キンブルのような気分であり、むしろ、ちょっと楽しみでもある。キンブルは、殺人者としての濡れ衣を着せられて警察から追われている、寡黙で渋い男であるが、そんな悪夢のときは、決まって寝汗をかいて首のあたりが“濡れ衣状態”である。
このような、“夢見る“自分とは、一体、脳のどこに居るのだろうか。光景や情景は、おそくら視覚情報として体験したことには違いないが、それが実体験である場合もあるだろうし、また、テレビや映画などで経験した視覚情報であることもあるだろう。そのような“視覚情報”は、網膜の神経細胞から視神経を通り、側頭葉底部にある外側膝状体を経て後頭葉極のブロードマン17野(一次視覚野)に到達したものと言うよりは、扁桃体に投射したものに違いない。
網膜から扁桃体に入る“視覚情報”は、“物”の姿・形を認識するのではなく、快・不快、好き・嫌い、安心・不安、恐怖・快楽、陰・陽というような、相反する気分を感じるという臨床的な知見が明らかにされている。網膜神経細胞からの視覚情報が伝達される後頭葉後端の左右の一次視覚野が破壊された患者は、完全に視覚情報の認識ができなくなるが(皮質盲という)、一方で、扁桃体に入力した網膜情報によって、快・不快、好き・嫌い、安心・不安、恐怖・快楽、陰・陽というようなムードを感じることができると言う。つまり、“物”を見たときに、セットで記憶される“扁桃体ムード情報“が脳内で息を吹き返すことが、第一義的な“悪夢”の本体であって、それに随伴して、昔見たような光景が見えてくる、という具合ではなかろうか。今夜も、扁桃体がズキンズキンするかと思うと、すこしわくわくするのであった。

◎函館下宿物語(1)◎
中学2年のとき、横浜から函館に引っ越した。親の転勤のためである。家は某テレビ局の官舎で、400坪の土地に、100坪くらいの平屋の家。庭にはリンゴの木。バーベキューなどもよくやっていた。何不自由ない生活だった。そして高校3年の6月に、親達は、私を下宿に残して転勤のため、横浜に戻っていった。函館に残された理由は、もう少しで卒業だから、ということだったが、中学1年のときからの学費を払うことを躊躇したようである。下宿生活が始まる6月のある日、その広い自宅から高校にいつも通り登校し、午後早い時間、親が決めてあった賄い付きの下宿に初めて“帰宅”することになった。函館市時任町の片隅に、それはあった。
大家さんは、当時、70歳は軽く越えていると思われる老夫婦。おばあさんは小柄で優しそうな方だったが、おじいさんは、いわゆる明治の頑固親父、というような風貌だった。なんか疲れそうだな、とため息をつきながら玄関を入った私は、1階の台所兼食堂の向こう側の奥の部屋に連れてゆかれ、ここがあなたの部屋よ、と言われ、あっけにとられているうちに、背中のほうで、ふすまの扉がすっと閉まった。そのあとの静寂がどのくらい続いたか。
暗い。寒い、というよりは冷たい。6月なので、もう少し暖かくてもいいだろうし、昨日まで住んでいた家は、もっと暖かく、そして明るかった。それにしても、暗く、冷たい。一日中、陽があたらないような座敷牢のような部屋。思わず、親が運んであった段ボールの中のアノラックを着込んだ。親が高校での集団下宿説明会で、厳しそうな大家さんだから、ということで、ここの下宿にお世話になることを勝手に決めて、しかも、下見もなにもしていない。部屋も冷たいが、それ以上に、ずいぶん冷たい親だ。そのときの感情は、今もまったく変わらない。
これからどうなるのか。そして、急に押し寄せた空腹感。何か食べたい。何か飲みたい。が、何もない。家財道具といえば、身の回りの服や勉強道具が段ボールに入れられて届けてあるだけだった。もう、その日の昼に、親は函館を去っている。何てこった。腹が立つ。そして、その次に、またあの感覚。腹が減った。何か飲みたい。
◎函館下宿物語(2)◎
いつもなら、リンゴが剥いてあったり、マスクメロンがあったり、食べるものに困ったことがなかったわけだが、一瞬にして、現実が変ったことを悟ったわけだ。とにかく、何か食いたい。夕食まではまだ長い。何か食いたい。その一心で、近くのスーパーに行ったが、手持ちの金との相談で、45円の食パン一斤だけを買ってきた。部屋に戻り、食パンに食らいつく。美味い、というより、ホットする。いや、ホットする、というより、美味いのだ。しかし、水分がないと、だんだん飲み込めなくなってくる。が、コップすら持ってこなかった。気の効かない薄情な親だ。そうは言っても何にもならない。ガラス製の大きなペン立ての中のペンを、机に放り出し、隣の台所の水道を捻り、水を一杯に入れて、部屋に戻り、一気に飲み干す。なにか、涙が溢れ出てくるぐらい美味く、そして侘しい感覚に打ちのめされた。食パン一斤をあっという間に、何もつけず、平らげたわけだが、あんなに、美味い水とパンを、いまだかつて食べたことがない、おまけに、あんなに寂しい薄くらい部屋で、独り。それも、数ヶ月後に襲ってくるオイルショックで、食パンが一気に3倍に値上がりすることも予見もできないまま。
もう陳腐な言葉だが、飽食の時代、と言われる。料理、グルメというと、なにか贅沢な響きがあるが、料理とは、食べて美味いと感じる生物学的な環境で自然と美味いと感じるものを提供することなのだろう。私の料理の原点は、あの時のパンと水にあったのかもしれない。乾いた砂に水が吸い込まれるよう、そんな状況を意図してキッチンに立つのが、料理の本質なのだろう。何も贅沢をすることはない。食材をその時に応じて、生かせばいいわけである。あの時のパンと水が、あの時の私にとっての、最高の食材だったように。
下宿生活をはじめた当初、何も家財道具というものがなかった。やがて必要になる石油ストーブは大家さん家のものを借りたのだが、晩秋になって寒くていられなくなって初めて使ってみたところ、芯が焼き切れていて煙しかでなかった。そのことを大家さんに言えばよかったわけだが、当時のワタシは遠慮がちだったのだろう、そのまま、使わずに一冬過ごしたのだった。
◎函館下宿物語(3)◎
雪の季節になってくると、二重窓の外側の窓の立て付けが悪くなっていて、当然のように隙間が形成され、その周囲に雪の吹きだまりができてしまう。家の中に雪が積もるなんて、初めて経験した。当然寒い。だが、ストーブがない。あるのは、600ワットの電熱器だけである。南部鉄器の小さな急須があったので、それでお湯を沸かして、なんとなく暖かいような気持ちになるわけだが、すぐに冷えてしまう。なので、冷える前に沸いたお湯を飲んでしまえばよいと思い、中にお茶っ葉を放りこんで、お茶で体を温める。そんな生活をしていたわけだが、緑茶の葉っぱを入れるのに、いつもほうじ茶になって出てくるので、なんか変だな〜と思っていたわけだ。
ある日、茶っ葉を切らしたので、仕方なくお湯だけを飲もうとして、愕然とした。茶っ葉を入れなくても、ほうじ茶、なのである。なんで?と思って、飲んでみたところ、鉄臭い。なんだ、南部鉄の錆びをずっと飲んでいたのか。鉄欠乏性貧血にはいいのかもしれないが、若い男には関係ないし、鉄を飲んだからと言って、鉄人になれるわけでもないし、少しは体重が重くなったかって、なるわけない。南部鉄器の急須を見ると、いつも思い出すのは、あのときの鉄の臭い、である。
風呂は使わせてもらえなかったので、歩いて5分くらいの銭湯にときどき通っていた。ときどきが何日おきか忘れてしまったが、金もなかったので、そんなに頻繁にいくわけには行かなかった。とにかく、ひもじかったので、金があるのならば、何か食べたかったし、寒い季節になると、下宿に戻ってくるころには体が冷えてしまっていたので、億劫になっていたのだ。下宿の部屋の机の前においた電熱器は、冬ともなれば、暖房代わりに使っていたが、夜中になって、大家さんも下宿人も寝てしまわないと、ブレーカーが落ちてしまうので、寝袋に足から腰までつっこんで、上はアノラックに毛糸の帽子、という格好で過ごしていた。南部鉄器で鉄を飲んでいたのも、そんな深夜の一コマである。
◎函館下宿物語(4)◎
それでもたまに銭湯で風呂に入りたくなるわけだし、そんな帰り道、無性に食べたくなるのは、甘いものだった。若かったんだろう。エネルギー補給にはテットリ早いのがグルコースである。そのころの、甘いもの、と言えば、ファンタオレンジ、エクレア、そして大福、である。風呂上がりに飲んだ、微炭酸のファンタオレンジの美味しかったこと、いまも鮮明に覚えている。昨今のファンタとは、おそらく甘味料が違うのだろうが、舌を刺激する炭酸とあまいオレンジの香り。銭湯の想い出といえば、ファンタオレンジだ。
でも、ジュースだけでは腹に溜まらないわけで、エクレアか、大福が欲しくなるわけだ。その当時、大福は1個15円だった。千代台の路面電車の停車場の近くに和菓子屋があって、たまに買うことがあったが、ある日、どうしても大福が食べたいものの、手持ちの金がまったくなかったことがあった。そこで、その和菓子屋の向かいに古本屋があったので、下宿に一旦戻り、使っていない新品同然の参考書を何冊か持っていって、90円に換えたことを、まだ覚えている。おまけに、どこかで万引きしてきたか、学校で誰かのものを盗んできたんだろう、という目で私を舐め回した店主の親父の顔。結局、生徒手帳を出して、名前を控えられ、90円を貰ったわけだが、すぐさま、その足で和菓子屋に行って、大福6個を購入。消費税がない時代でよかった。
下宿に帰る道すがら、歩きながら1個食べ、2個食べ、3個食べ。数分後、下宿についた頃には残っていなかった。下宿の部屋の電気をつけて、薄暗く寒い部屋の中央に敷いてあった万年床に寝転がっていたら、遠い港の方から、ぼ〜、という汽笛。なんか無性にわびしくなって、布団を頭まで被った。美味しいもの、大切なものは、最後に取っておく、という根性は、あのときに刻印されたのかもしれない。
◎青函連絡船のカレーライスー下宿を去る夜ー◎
卒業式のシーズンにいつも思いだすことがある。私は高校の卒業式をすっぽかしたのだ。
中学2年から住んだ4年半の「函館」。最後の10ヶ月は、初めてのヒモジイ下宿生活。そんな生活も残り少なくなった高校3年の2月ころ、卒業試験も終わり、東京への帰り仕度を始めた。10ヶ月過ごした部屋には、布団とわずかばかりの身の回り品しかなかったので、引っ越しの荷造りは簡単だった。それよりも、処分しなければならないゴミのほうが多くて閉口した。このころになると、既に現役合格などは念頭にまったくなく、中也や朔太郎の詩を読み耽ったり、なにやら訳知り顔で詩を書いてみたり、ブラームス交響曲第1番のスコアブックと睨めっこしたり、ほとんど廃人同様の生活をしていたわけだ。氷が張る冬になると、近くの市民公園の野外スケート場から聞こえてくるフィンガーファイブの浮っついた歌声が、妙に寂しく感じた感覚は、あれから40年も経とうとしているのに、今も自分の体の一部である。
中学2年の夏休みに東京から転校し、強烈な想い出が詰まった「函館」。東京から函館に引っ越した初めての8月の夜は暗くなるのが早かった。そして初めての朝は、布団の中で、サッカーの分厚い膝までのストッキングを探して履くくらい、寒く感じた。10月ころにはミゾレが降って、それでもみんなは傘をささない。こんな事ひとつとっても新鮮な出来事だった。冬になり手袋。手袋を「履く」って? 履くのは、そりゃ、靴下だよ、手袋は、する、でしょ?!なんていうような戸惑いも、新鮮だった。ともかく、若いうちは吸収力がある。函館の空気感にすぐに馴染んで、北海道弁も体に染み付き、好きなサッカーをグランドで、そして冬には、体育館でよくやったっしょ(←北海道弁)。なまら楽しい日々だった。因に、“なまら“は、本当に、すごい、とてつもなく、というような強調語である。
中学の担任は、担任を初めて持った若い美術の男性教師で、何事も、熱く語るタイプだった。三島由紀夫が割腹自殺を遂げた翌日のホームルームで、そのことを取り上げた。どう思う??と、新聞も読んでいない私にいきなり話を振った。えっ、その話、何?? 私はその事件を本当に知らなかったわけだが、知らない、というのも恰好わるいので、眉間にしわ寄せて黙っていると、「おまえは、黙秘か、、、」なんて、“議論”に負けたハンカクサイ奴に向けたようなストレートパンチが飛ぶ。 今ならば、割腹自殺・介錯、なんて言葉を聞けば、生々しい現実的な光景が浮かぶわけだが、その時は、一体何がおきたのかもわからなかった。因に、ハンカクサイは、恰好わるい、気味悪い、のような、なまらネガティブな言葉である。
そんなことは、ほんの少しのエピソードだが、函館に中学生のときに転校してから、深夜放送を聞くようになり、ほとんど朝方に寝るような不規則な生活。雪が降って積もった雪に、ずぼずぼ長靴が埋まり、春には砂まみれで真っ黒くべちょべちょになり、そして、そのあとは、ほんの短い夏の日々。でもすぐに、朝、布団の中でサッカーのストッキングを履いている自分がいる。
そんな生活を何年か繰り返し、沢山の想い出を胸に、高校三年の最後の冬の夜、青函連絡船で函館を離れる日がやってきた。下宿のおばあさんが船に間に合うようにと、気をきかせて、早めの夕食にしてくれて、下宿人数名に、“見送りに行ってあげなさい”と言ってくれた。それは、おばあさんの親切に違いはなかったのだが、学校や学年も違い、下宿生活の間、無言で夕飯を皆で食べる時間しか共有していなかったので、ほとんど口をきいたこともない。今夜これから、4年半の「函館」とサヨナラする大切な瞬間がやってくることを考えると、下宿の人達に見送られるのが、どうしても我慢できなかった。早い夕飯を食べて、駅までの市電のシートに座って、みんな黙りこくっている異様な緊張感。せっかく来てくれたのに、本当に悪いことをしたと思うのだが、市電を降りて船の改札のあたりで、“切符をなくした”と嘘を言い、わざと船に乗り遅れて、その結果、みんなと別れて、どうにかこうにか、函館駅で一人きりになることができたのだ。
何時発の青函連絡船だったのか? 乗船予定の船に確信犯として乗り遅れたので、次は、確か夜中12時の青森行き。もちろん、青森行きしかない。つまり、自分には、昨日まであった自由は、もうない。バイオリンの蛍の光の音色と共に、ゴンドラが鳴り響き、少しづつ船体は港から離れてゆく。船の下には黒く渦を巻く泡状の海面。思春期を過ごした4年半の、新鮮で、切ない強烈な想いが、船の下の泡沫となって少しづつ過去のものになり、架空の物語の断片になってしまう。昨日まで過ごした街の光がだんだん点状の小さな輝きとなり、やがて消えてしまうような焦燥感、喪失感が襲ってくる。デッキの上で、いつしか、古ぼけた木の手すりを、小さく、そして強く、なんども拳で叩いていた、どうして私は今ここにいるのだ、と。数時間前まで「函館」にいたはずの自分を、失いたくない、と。
もうこのまま、二度と、函館に戻ってくるのはよそう。
1ヶ月後の卒業式には一旦戻ってくるつもりにしていたが、船の上から見えるひとつひとつの思い出を瞬間冷凍して永遠のものにするために、もう函館には戻るまい、と心に誓ったのである。どれだけの時間、デッキに居たか。もう向こうは真っ暗闇。学園祭の夜にみんなで登ったはずの、函館山のシルエットも見えない。自転車で走った根崎の浜も、黒い海の向こうに判然としない。粗い岩肌の立待岬は、どこかに消えてしまったのだろうか。なかば放心状態で、揺れるデッキからフラフラと船内に戻り、小さな食堂でアルミ製の皿に盛られた、少しばかりカレーライスを食べながら、3月の卒業式はすっぽかそう、と決心したのである。春になるといつも、その薄っぺらなボリュームの、しかし、思い出いっぱいのカレーライスが脳裏に浮かび、脳底部の嗅球(olfactory bulb)から、黄色いカレー臭が脳内に漂うのであった。

◎しょっぱいフィッシュ&チップス◎
神経研に赴任して3年くらい経ったころ、変性疾患のグリア病変の共同研究のため、1年間休職しロンドン大学精神医学研究所・神経病理研究室に向かった。小学低学年の二人の子供と私たち、一家四人で成田を発ち、やがて、ロンドン、ヒースロー空港へ着陸したわけだが、直前に上空から見たロンドン郊外の夕方の住宅地。もう10月も30日になっていたので日が暮れるのも早く、おまけに、黄色い乏しい街灯のためだろうか、ずいぶん暗いな、という第一印象は、それからの不安な生活を予感させるものだったのかも知れない。
とりあえず入国1日目は、ヒースローからタクシーで市内に向かい、予約してあった安ホテルBarkston Hotelに泊まった。日本からヨーロッパへ行くと決まって朝早く目が覚める。翌日31日朝、これから1年間住む予定のウィンブルドン近くのNew Maldenという街のsemi detached houseに入居した。正確にいうとそこはロンドンではなく、ロンドン南西のサリー州であった。日本を旅立つ前に地元の不動産屋とコンタクトを取り、身の丈にあった物件を決めていたので、ホテル暮らしをせずに入居できたので良かった。しかし、入居したその日の午後、地元の子供の仕業か、窓ガラスに小石が投げつけられたり、夜の食料を調達に買い出しで外に出た際、住宅地の雰囲気がちょっとばかり荒れているような印象があったので、なにげに不安な入居初日であった。子供らは日本で小2と小4で、ロンドン日本人学校ではなく、地元の公立学校をこれから探すことになっていたので、それもあってか、不安は結構大きかった。いい加減な親であることは、昔も今も変わらない。
借家の大家さんはイギリス国籍ではあるが、エジプト人の中年女性で、シャフィーさんという、とても気さくで親切な人だった。入居の午後に家に来て、あれやこれやと入居時の家具や設備などのチェック(inventory check)をして慌ただしく帰っていったが、相当な慌て者のようで、玄関先にバッグを置き忘れていった。案の定、すぐに電話があって夜7時ころ取りにくるという。ところが7時になっても8時になってもやってこない。まあ、こっちは時間にルーズだからなあ〜、と家族と一緒にリビングのソファーに座っていたとき、玄関のドアのピンポンが鳴った。“やっと来たよシャフィーさん”といってリビングから玄関に行き、扉の硝子窓を覗いた瞬間、血の気が失せて全身が凍りついた。確か、Oh No! だ〜め!だ〜め!というような仕草をしてリビングに戻り、家族に異変を気づかれぬよう、ソファーにわざとゆっくり座り、誰だったの?シャフィーさんじゃなかったの?という問いには返答できず、唇が一瞬で乾き、足が振るえ、心臓も振るえていた。あんなに怖い思いをしたのはいまだかつてない。
異邦での入居初日であること、思ったより荒れた雰囲気の住宅街であったこと、昼間ガラス窓に小石を投げられたこと、子供たちの通う学校が決まったとしても馴染めるかどうか、これからどんな生活が始まるのか。とっても不安なその夜に、こともあろうか、玄関扉の窓の外に立っている『頭からドスグロイ血を流した青白い顔の少年』。この光景のことは、帰国する直前まで家族に明かすことのできなかったくらい、人生、最初で最後の怖い体験だった。
あの夜、リビングの食卓に並んでいたのは、日が暮れる前に近くの店で買ってきた、油っぽくなった新聞紙に包まれた大量のフィッシュ&チップスだった。モルトヴィネガーソースを振りかけて食べる流儀は、帰国してから覚えたわけであるが、しょっぱい夜のそんなこんなで、これから1年どうなるものかと、なかなか寝つけなかったのだった。やがて年があけ、生活にも慣れ、帰国が近づいたとき、英国神経病理学会誌「Neuropathology and Applied Neurobiology」の編集長から、総説執筆の謝礼として300ポンドの小切手をいただいたが、未だ換金せずにチップスの塩気と油が染み付いたままである。“それはただのハロウィンの子供じゃなかったのか??”と腑に落ちるようになってきたのは、そんな、帰国も間近になった翌年の10月頃であった。
◎横浜の人間が多摩川を越えてうまくやってゆけるのか?◎
内科1年、病理半年、神経科半年の研修の後、三杉教授のお誘いを受け母校・第二病理の助手に採用していただいた。研修医時代には、柳下三郎先生、原正道先生に神経病理のご指導をいただき、また、神経科の神経病理グループの天野直二先生(現・信州大学精神医学講座 教授)の背中を追っているうち、神経病理で生きてゆきたいと思うようになったのは、自然なことだった。しかし、神経病理だけで禄を食むには、東大、新潟大、九大、鳥取大での教授ポスト4席、東京都の3研究所(神経研、精神研、老人研)の研究員ポストが10席程度あったに過ぎない時代でもあった(今はもっと少なくなってしまったが)。
浦舟校舎の病理に入局した日、研修でお世話になった神経科・横井晋教授のお部屋に押し掛け、将来への気持ちを縷々申し述べたところ、その場で神経研の、後にボスになる研究員に電話をしてくださり、面談をしていただく運びとなった。面談というより、神経研近くの居酒屋での“酒量の試験”だったが、「新井さん、いつか声をかけるか約束はできないが、論文は書いておけよ」と言われ酩酊状態で終電に乗った。自分の足で歩き始めた瞬間でもあった。
それからと言うもの、解剖・実習等のノルマ以外は、“その時”のために、ひたすら論文を出す仕事に精を出し、一方では前途茫洋とした不安な日々を送っていたわけだが、昭和天皇が崩御された翌日の寒い夜、「新井さん、まだその気はあるか?」という、5年振りの自宅への電話の声を聞くなり、「お願いします!」と、焼酎のお湯割りを右手に持ち、直立不動だった自身の姿は、今も忘れない。
ジョブセミナーもどうにかクリアして、平成元年11月にあこがれの神経研の主任研究員の辞令を都庁でいただき、揚々とした気持ちで西国分寺の研究所へ初出勤したとき、待っていたのは本題に掲げた、当時の副所長の辛辣な一言であった。天から地に落ちる“乾いた音”を伴ったあの苦い一言のお陰で、母校を離れて他流試合をしてゆく“強い気持ち”を維持し続けられたのかも知れない。以来24年、うまくやれたか判らないが、新しい研究所に再編された今も、師と仰ぐアバンギャルド・岡本太郎の言葉のように、“常に新しくあり続けなければいけない”という命題に対峙したいと思っている。
◎角館に降るカサブランカの雪◎
その冬は、雪が多かった。3月、角館の温泉に浸かる旅も、案の定、大雪に見舞われた。
大雪の中のこじんまりした露天風呂。見知らぬ男が3人ほど入れば、気まずくなるような、そんな奴だが、幸い、冷気の助けによる湯煙が、視界を遮り、ひとりにしてくれている。雪のひとつひとつが、湯の波間に消えてゆくさま。吐息も白く、そして、疲れた“気持ち”にとっては、熱すぎる湯のせいか、体はまだまだ緊張から解放されない。見上げれば、目まぐるしく変る空の明暗。それはあたかも自分の日常の迷路のようでもあり、そこから乖離して、次第に湯の中で解凍され流れ出てくる昔の自分がいる。“ああ、自分は何をしてきたのだと・・・・”という青臭い詩人のセリフとともに聞こえてくる、諦観にも似た呟き、“もう十分・・もういいよ、このへんで・・・”。
こんな時、雪の降る囁きの声以外には聴こえないものだが、ふと、我に返ると、湯気の向こうから、少しフラット気味の鼻歌が聞こえるようだ。As time goes by、、、。まさか。昔にタイムスリップした丁度いま、その歌だけは、見知らぬおじさんの口からは聞きたくない。やめてくれないか。
ずっと若かった時代。深夜、ふとスイッチをいれたテレビから映し出されてきたのが、この歌が漂う映画、カサブランカ。洋画など見た事もないのに、セピア色の画面に引き込まれてゆく。初めての、そして懐かしくもある不思議な時間。ハンフリー・ボガードのボギーもよかったけれど、渋い男にしては声のトーンが高すぎる。一方、イングリッド・バーグマンのイルザの瞳の奥の視神経の眩しいほどの白さ。視神経など、眼底検査でもしなければ、解剖学的には見えるはずはないのだが、確かに白い、涼しい「視神経」が印象的だった。そんな目に見つめられて、やむなく歌い出したサムの“As time goes by”。あれからもう30年余。いつのまにか、そんな思い出も忘れてしまっていた。
雪の露天風呂。学生時代の雪の函館、近くの市電の音、足下の雪を踏みしめる乾いた雪の声、そして遠くの連絡船の汽笛。そんな情感を思いださせる季節はずれの雪の街。若い頃など、もう30年以上も前のことだが、体が温まるにつれ、懐かしく、そして、現実のものとして体表から浮き出てくるのは何故だろう。そんな時に、隣から、容赦ない、カサブランカのあの懐かしい歌、As time goes byの鼻歌。しかも、見知らぬおじさんが私に歌ってきかせるが如く、最悪のシチュエーション。せっかくの旅が台無しだ。
思わず、手を伸ばし、岩の上に降り積もった雪を握って潰してみたが、小さな氷のように硬くなってしまった様は、濃縮された自分の心のようでもあった。もちろん、そいつの運命は、熱いお湯の中で消えてしまったわけだが、その湯に自分が浸かっていると思うと、少し滑稽でもあり、悲しくもあったのだ。
As time goes by.
“時の過ぎ行くままに”と誤訳されることが多いが、正しい訳は、“時が過ぎても”である。時が過ぎても、若いあの時の心のまま、転がっていたいものである。

◎“もやもや”したもの◎
脳血管造影検査で、特異な脳血管異常の所見が、煙のように“もやもや”見えることから、もやもや病(Moyamoya disease)の名称が国際的にも使われるようになったのは、日本人が発表した1969年の論文に端を発するわけだが、これひとつとっても、日本人にとっては、“もやもや”という言葉はしっくりくるのだろう。誰が何と言っても、もやもや、しているんだから、しょうがないが、この感覚は欧米人にはわからないことは、経験的に察知できるのだ。
研修医のころ、病棟での仕事が遅くなり、朽ち果てそうな2階建ての研究棟の片隅の、神経科の研究室に寝泊まりしていたことがしばしばあった。寝ると言っても、丸椅子を4つくらい並べて、器用に寝てみるわけだが、案の定、落ち着くわけもない。そんな夜中の空気の中で、あれやこれや、脳病理標本を顕微鏡で観察していた全く素人の研修医の目に、微笑みながら飛び込んできたものは、神経細胞の周りをとりまく“もやもや”した帯状の光景だった。ヘマトキシリン・エオジン染色でもボディアン染色でも、パッとした染色性を示さない“もやもや”した無構造な風情であったが、なぜか、不思議に綺麗な光景として、目を釘付けにした。同じものを観ても、何にも感じることなく、そのまま夜を明かしている自分だったら、今頃、もうちょっと世間的には“偉く”なっていたかもしれない。なぜならば、そのときに観てしまったものは、誰にとっても動かしがたい、無骨な実像(事実)そのものであり、一方、自分の活動を正統化する理論武装をして、虚像かも知れない仮想敵国と戦っている姿のほうが、何か“すごく”見えて、説得力があるからでもある。顕微鏡で観たものが“綺麗だ”、“不思議だ”と感じた気持ちがモチベーションなんですよ、と言ったって、うつろう人の気持ちには響かないのだろう。ただし、そのような情緒に心動かされる人のほうが、親しみを覚えるが。
観察していた脳の場所は、小脳の歯状核。疾病は進行性核上性麻痺だった。そのときは、病変なのか? 気のせいなのか? 素人に毛も生えていなかったので、判る筈もないわけだが、不思議な美しさに、“意味のありそうなもの“を感じ取ったことだけは確かである。ただ、そうは言っても、心惹かれた“もやもや”したものを、病理学的になんと表現していいのやら、気持ちも“もやもや”してくる。Greenfield’s Neuropathologyを調べても、どこにもそれらしいことは書いていないし、写真もない。やっぱり気のせいなのかと、もう一度顕微鏡を覗いてみる。
そんな日々を繰り返しているうちに、「神経研究の進歩」という由緒正しい医学雑誌に掲載されていた、「小脳歯状核のグルモース変性」を扱った(あとで知ったが)高名な泣く子も黙るS教授の総説に遭遇した。なるほど、同じ写真だな、と。グルモース変性は、grumose degenerationの和訳である。そのgrumoseは、辞書で調べると、植物の根が累々としている様、牛乳や血液が凝固している様、のような意味であり、ちょっとした塊のようなものを意味している、あまり馴染みのない形容詞である。わたしが観た“もやもや”も、観ようによっては、小さく淡い塊が集合したようなものでもあり、それはそれで、言い当てているようにも思えた。
その後、凝り性のわたしは(飽きるのも早いが)、小脳歯状核ばかりに注目して、歯状核神経細胞の変性パタンには3種類があることを計測学的に明らかにした。また、このgrumose degenerationの本体である“もやもや”は、プルキンエ細胞の軸索終末の発芽を思わせる超微形態変化であること、また同時に、歯状核神経細胞の変性も同時進行する、小脳遠心系の系統的な特異な病理変化であることを明らかにした。ただし、英文の論文にはなったとはいえ、欧米の教科書には、全く触れられていない病変であり、何か釈然としない“もやもや”は残ったままであった。
その小脳歯状核のgrumose degenerationが、Prof.Anzilが進行性核上性麻痺の研究報告論文(1969)の中で、ちょっと軽い気持ちで使ったgrumose degenerationという言葉が、後年、日本の神経病理を牽引していたS教授の引用によって、日本(邦文)だけで一人歩きした言葉であったこと、そして、それを知ったProf.Anzilが、それについて困惑しているという手紙をわたしがいただいたこと、さらに、その数年後にわたしがが偶然にも中脳黒質で見つけた、当時“名もない”病変が、実は、Prof.Anzilが記載したgrumose degenrationの本体とは全く別ものである、1900年代初頭にパリのDr.Tretiakoffが最初に記載した中脳黒質でのgrumose degenrationそのものであったことなど、思いもがけない事実を探し当て、結果として、昔すでに知られていたことと、今はもう忘れ去られたことの、点と点のあいだを結びつけて、時には匍匐(ほふく)前進しながら、時には脚を痺れさせながら、うろちょろしたのであった。

◎膨れている言霊◎
医学部を卒業したのちの研修医1年目(1982)は、市中の総合病院の循環器、呼吸器、神経内科の混合病棟の新米スタッフとして、嵐のような忙しさに追いまくられる日々を、最初から最後の日まで過ごしていた。早朝から病棟を周り、午後は外来や検査の見習いようなことをして、夕方から胸部X線の読影、気管支ファイバー、心臓カテーテル、心電図などの勉強会。それが終わると、夜の回診をして、今夜は帰宅できるかどうか思案して、結果的に病棟にあった畳部屋で夜を明かす、という日も稀ではなかった。あるいは、少し早めに終わった日は、片道1時間半くらいかけて一旦帰宅して夕食をとり、1、2時間後には終電に乗って最寄り駅まで行き、タクシーを拾って病院に戻って夜を明かす、という日は、もっと多かったかもしれない。もっと要領よくできたはずなのに、新婚にありがちな“忙しさ”に酔っていた自分が滑稽でもあり、今振り返ると、一番嫌いなタイプの人間かも知れないが、その一部分の性根は、おそらく今も抜けていないのが、さらに恥ずかしい。
研修医2年目(1983)は大学の病理学教室の朝の光景から始まる。昨日の夜まで馬車馬のように働いていた生活が、一夜あけたら、あたかもNHK年末恒例の紅白歌合戦の直後に転ずる番組“ゆく年くる年”の冒頭の静寂のような空間。あくせく病棟に行くこともなく、じっとして顕微鏡で標本を観察する、静かな時間が朝っぱらからずっと続く。昨日まで、朝から晩まであくせくアクセクしていたのに、急に無重力空間にほっぽり出される。入局する意思を表明していれば扱いも違ったかも知れないが、半年後にはどこへゆくやらわからぬ、使い物にならない研修医は、訳知り顔の玄人集団のなかでは、邪魔者扱いにされるのが常である。
こんな静かな教室で、どうやって半年暮らそうかと思っていたところに、少し遠くのほうで、椅子に胡座をかいて座る体勢で顕微鏡を覗いていた、ちょっと強面の先輩が、今になって思えば救いの一言を投げつけてくれた。「みんな、よく判らないから、脳の標本を観るのが好きじゃないのさ。でさっ、君さっ、暇なんでしょ? だったら、脳の病理だけ勉強して、俺の症例の標本を観て、コメント書いてくれる?みんなのもやってくれると、君も大事にされるよ、あっはっはっ・・」 裸足に粋な雪駄を履いて、胡座をかいて椅子に座って顕微鏡を観ている素浪人風情の先輩のその一言が、その後の私の道程の入り口だったのかも知れないが、半年の病理学教室での研修の後、神経科で半年研修し、その後、またこの教室に教員として戻ってくるなど、誰も予想だにしなかった、もちろん自分も含めて。
便利な“変わり者”が来たということで、先輩から促されるまま(押し付けられるまま)、いろいろな症例の脳病理標本を観察することができた。たまに、寿司でも食べに行くか?と誘っていただき、どこへ行くかと思いきや、スポーツカーで横浜から沼津の寿司屋まで高速を飛ばす、ということが何度かあった。そんなこんなで、研修が始まってから多くの病理解剖の手伝いはしたものの、神経疾患の解剖症例はなかった。しかし、やがて3ヶ月ほど経った頃、オリーブ橋小脳萎縮症(olivopontocerebellar atrophy; OPCA)という臨床診断の症例の解剖を担当することになった。OPCAという疾病は、当時のいろいろな神経病理のテキストにも詳述されている疾患であり、その名の通り、オリーブ核、橋、小脳が変性する病気である。しかし同時に、線条体・黒質変性症(striatonigral degeneration; SND)という疾病において変性する場所である線条体、脳幹(黒質)などにも病変を認めることがあり、OPCAとSNDは違う病気なのか、同じ病気の範疇なのか(Oppehmeimerらが多系統萎縮症 Multiple system atropnyという名を用いて主張していたような)、という議論があることも、教科書には載っていたわけである。
このようなことを勉強しながら、標本を観察して所見をピックアップして、レポートにまとめることは、ビギナーにとっても比較的容易ではあったが、一応、先輩と一緒に顕微鏡を観てチェックしてもらうことは習わしであった。
一緒に顕微鏡を覗きながら、所見を説明していると、「この細胞、ちょっと膨れているんじゃないの?」と、観察している視野が大脳に移動したとき、とっさに先輩がつぶやくものの、OPCAという病気は(教科書的には)大脳の病気ではない。研修も3ヶ月になり、自分だけがたくさんの脳標本を観てきているので、「これだから素人は困る」と不遜にも心のなかで思いながら、「先生、OPCAという病気は大脳には病変はないんですよ、小脳や脳幹の病気なので・・」と返答したものの、「なんか膨れているな」と少しだけ不安になったことは、それから16年程経ってから、的中することになったのだ。
1989年、ロンドン大学精神医学研究所・神経病理研究室(Lantos教授)から、「OPCAとSNDに共通する病変としてオリゴデンドログリアの細胞体内に封入体がある」という研究成果が発表され、この2つの疾病は実は同じ病気(多系統萎縮症 Multiple system atrophy)である、ということの科学的根拠となった。この封入体は、glial cytoplasmic inclusion (GCI、邦名はグリアコイル小体)と命名され、やがて、GCIの構成蛋白がリン酸化αシヌクレインであることが判明し、シヌクレイノパチーという新しい疾病概念が生まれるなど、エポックを形成したわけだが、通常の染色ではほどんど目立たず、1990年代以降に汎用されるようになった特殊な染色であるガリアス(Gallyas)染色で明瞭に可視化することができる、きわめて特異な構造物であることも、後にコンセンサスが得られることになった。1991年頃、当時は比較的筆まめであった筆者は、GCIを発表したLantos教授に何度か手紙を書いては、あれこれGCIについて質問などを投げかけていたところ、「そんなに興味あるならば、いっそのことロンドンへ来てはどうか」というお誘いを受けて、翌年の11月に、家族を引き連れてロンドンへ旅立つことになったのである。
雪駄を履いて胡座をかいて顕微鏡を覗いていた粋な先輩が発した、病理学教室での研修の初日の一言がなければ、神経病理を専攻することもなく、やがてロンドンへ行くこともなかったかも知れない。一緒に顕微鏡チェックをしてくれたときに、識別が困難であった染色標本にもかかわらず、神眼で“膨れているもの”を見通したニュートラルな「つぶやき」が、そうさせるための必然の言霊のなせる技だったのでは、とは言い過ぎだろうか。最近、言霊を身近に感じるものとしては、きっとそうだったに違いないと思わずにいられない。“先入観のない者こそが、聞こえぬ声をとらえることができるのさ”と、右足だけを器用に胡座に折り畳んで、あの時と同じ赤いスポーツカーをモナコグランプリのように、あの世でもぶっ飛ばしているに違いない。

◎津軽の旅 2006 (1)◎
今年(2016年)の6月は弘前で第57回日本神経病理学会がある。今から10年以上前の2006年、津軽の旅をして以来の弘前行きである。以下、当時の日記を振り返ってみた。
------------------------(以下 日記2006)-------------------------
朝8時過ぎに東京を出発し、一路、弘前へ。八戸まで新幹線で3時間、そこから青森駅経由で1時間半。昼過ぎには弘前駅に到着した。チェックインしたホテルのフロントには、津軽の名家に誕生した第3子が男であった由の、昔の号外が置いてあった。太宰治、である。
弘前への訪問は25、6年振りだ。大学生のころに何かの全国集会が弘前であったので、東京から函館に飛んで、青函連絡船で青森に戻り、汽車で弘前入りしたことを、おぼろげながら覚えている程度だ。それはちょうど、ねぷたの頃で、弘前大学付近の宿泊所に雑魚寝をしながら、連日会議をしていたような気もするが、何の会議であったのすら、その辺はもう記憶にない。そんなことを考えながら、ホテルを後にして、弘前入りの途中に通った青森まで、奥羽線の各駅電車で戻ってみることにした。約40分、右手に八甲田連峰を見やりながら、ふと思いついた。青森港に保存停泊中の青函連絡船、八甲田丸を見に行こうと。
青函連絡船には若い頃、何度も乗った。生まれて間もなくの東京から函館へ(ただし記憶はないが)。その後、札幌、東旭川、旭川。売れない流しの演歌歌手のようだ。そして、小学校2年に旭川から東京へ。中学校2年の時の東京からまた函館へ。親は勝手なものだが、小さい頃は文句も言わずについていかなければならない。その後は、中学卒業の春休みにトランペットを買いに函館—東京の往復。高校3年、一人下宿をして初めての夏休み、東京への帰省往復、そして冬休みの往復。大学になってから、一度、函館放浪の旅。それらすべてが、青函連絡船であった。
そんな事を、ぼんやりと数えながら青森駅に降り立つ。駅前できょろきょろするまでもなく、黄色と白に塗られた八甲田丸が目に入る。なんだ、結構綺麗に手をいれちゃってるのか、と少し溜め息をついて歩いて近づいてみたが、次第に大きくなる船体には、長年の風雪に耐えきれなくなった錆が、いたるところに顕われてきていて、なぜかほっとしたわけだ。そう、あの時のままの連絡船だよ。シケで出ることができなかったデッキがあれだよ、乗船する時の木製の扉があれだよ、外の夜の海原を覗いた小さな窓の奥に映る少年の影が、あの頃の僕だよ。そんな感傷みたいな感覚に包まれながら、北津軽の旅が始まったのである。
◎津軽の旅 2006 (2)◎
駅前に戻ったのは3時近くになっていたのでランチができる店はあまりない。無駄に彷徨っていてもいかがなものか、ということで、すぐ目に留まった食堂に入ってみた。土地の者ではないので、何かおすすめはありますか?と聞くと、店のおばちゃんが自嘲気味に、こっちはあんまりね〜のさ、けの汁くらいしか、と言って写真つきのメニューを見せられた。けの汁って何?? けの、ということは、ハレじゃなくて、ケの汁?? つまり、ハレの日のものじゃなくて、普通の日常生活の中の、普通の汁?? 写真の中には何やら野菜の細切れみたいな具が沢山入っているスープのようにも見えるのだから、特別なものじゃなさそうだ。でも、こんなものしか、と言うのだから、なんぼのものなのだろう、ということで、けの汁定食を頼んでみた。あとで調べてわかったことだが、けの汁は、野菜・根菜やこんにゃくの細切れのごった煮スープということであって、ケの汁、ではなく、米が貴重だったころの、米代わりのお粥、つまり、粥の汁、縮まって、けの汁、だそうな。醤油ベースでも、味噌ベースでもいいようだ。つまりこれって、ミネストローネとか、ズッパベヌデューラといった、イタリアや南フランスの田舎料理のスープとおんなじである。どこの人でも同じようなことを考えるのだな〜、と妙に感心していると、連れが呟いた。「これって、豚肉の入ってない豚汁じゃない?」 まあそうかもしれないが、津軽版ミネストローネとして理解するのがいいのだろう。
八甲田丸、そして、けの汁に触れて、夕刻奥羽線で弘前に戻った。7時過ぎていて少し雨が降っていた。もちろん陽は落ちている。そうとなれば、やっぱり、何かで身体を温めなければと思うのは、普通の生理的な欲求であり、さっそく、ホテル近くの居酒屋の暖簾をくぐってみた。久しぶりの土地で、おまけにふらりと入ったわけなので、特別の思い入れはなかったが、結果としては、次の夜も利用させてもらうことになる、とても居心地のよい店だった。 炉端を囲むコの字のカウンターに、小さな小上がり。奥には大将が黙々と作業し、カウンター越しの炭焼き場には、若いお兄ちゃんが一人。そして、厨房とホールを行き来する見習いのお兄ちゃんがひとり。小さい店とはいえ、繁盛しているのでスタッフ3人じゃちょっときついのではないかとぼんやり見やっていたが、休むことなく、無駄口きくわけでもなく、返事はハイ!はい!っと、てきぱききびきび、本当に気持ちのいい仕事っぷりだった。
まずは、貝焼味噌を頼んでみた。これは、おおぶりのホタテの貝をお皿にして、ホタテをひとつ真ん中に置いて、溶き卵と味噌味の出汁を入れて、ネギをまぶして炭火で半熟状に焼いたもので、あつあつの卵とホタテを、ふ〜ふ〜しながら、ビールで楽しむ定番メニューだそうだ。一つ100円。ホタテも立派で、とても気に入った。 さて次にイカの丸焼き。これは何の変哲もない、イカの炭火焼きだ。と思っていたが、さすが、新鮮なイカが入手できる土地柄である。イカの中には腑がそのまま入っていて、それ丸ごとの炭火焼きであった。イカの身もコリコリしていて美味しかったが、火が通って湯気のでている腑と一緒に食べるイカ焼きは、およそ東京では無理だろう。東京では、どう考えても鮮度は落ちているので、腑が入ったままのイカ焼きなんかがでてきたら、却って大丈夫かと心配になるところだが、弘前の夜、テキパキキビキビとした手つきで目の前で焼かれたイカの丸焼きは、とても愛おしく思えたわけだ。(続く)
